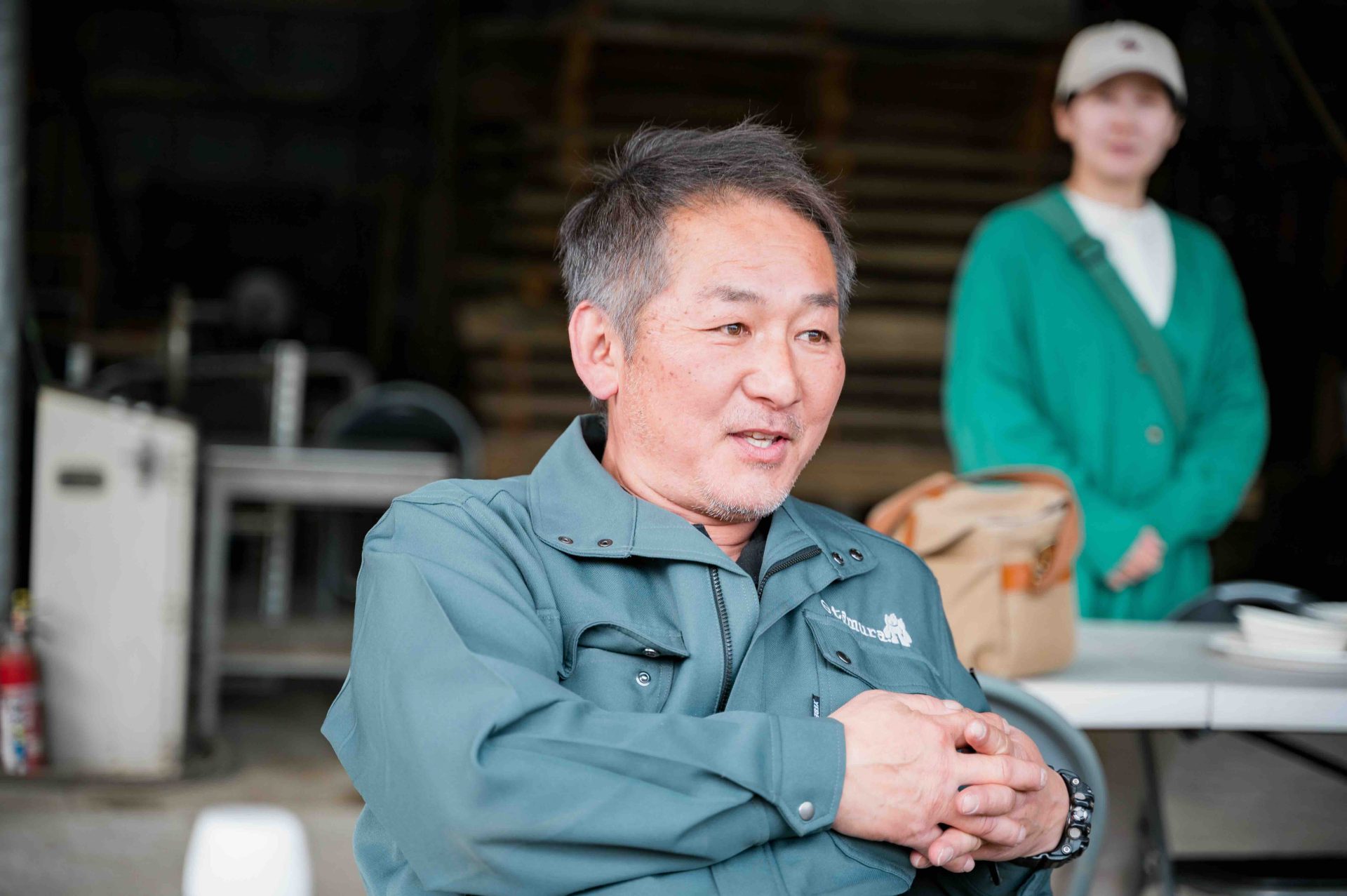僕は現在修士論文に向けて研究活動を行っている。テーマは左官である。
2025/07/14
今日の午後は、ものつくり大学の大学院授業に参加した。僕は現在修士論文に向けて研究活動を行っている。テーマは左官である。内容としては、左官屋さんが楽しく仕事ができて、収入がもう少し上がって、そういう左官屋さんになりたいと思う若者が今よりも少し増えるためにはどうしたら良いかということだ。前にもこの日記に書いたけれど、2020年の国勢調査で左官屋さんの総人数は58000人くらいになってしまったことがわかった。そして65歳以上は28000人くらいいることもである。今はそれから5年が経っている。このままの状況が進めば、日本から左官屋さんがいなくなる?と思うとそんなことはないと思う。きっと人数が減って、希少価値も上がって、一部の伝統系の楽しい仕事をやりながら高収入、という人達は残るだろうけれど、でもその人数が足りない状況になってしまうことは間違いない。
今の学生達と話をしていると、左官の技能5輪に参加したような子でも左官屋さんにならないことがある。その理由は、低賃金だ。ではどれくらいの収入があれば良いのか。現在の左官屋さんの職人として一人前の人の収入は、450万円くらいが一般的だ。もちろんそこから経営者になっていく人は別だけれど、みんながみんな経営者になるわけでもない。僕は職人として勤めている人にとって、なんとなく理想として納得がいく目安は600万円くらいの達成であるような気がする。それでも足りない人は、経営者を目指せば良いと思う。3人くらい人を雇用して、営業をして、仕事をやって・・・これは大きな企業の係長くらいの仕事だから、つまりは管理職と言えるだろう。そこでの能力は、壁塗りのうまさだけではダメだ。当然、左官に関する歴史、知識、デザイン、コスト、素材を仕入れたり仕事を助け合ったりするためのネットワーク、経営に関する知識、資金、・・・すべてがなければ成立しない。だからここでの年収は600万円からだいぶあがる。1000万円の人もいればそれ以上の人もいるかもしれない。その上がる程度は、やる仕事の量と質によるだろう。
でも、こういう未来を見せて貰えば、もしかしたら左官になってみようと思う学生も出てくるだろう。そしてこれは住宅デザインも同じ、大工さんも同じ・・・そして全ての職業に当てはまる考えだと思うのである。
今の学生は真剣に将来を考えている。でも学校では真剣に考えていても、そういう未来を見せてくれることは無い。就職相談会でも無理だと思う。だって独立した後のことなど、ほぼ誰も説明してくれないのだ。人生は独立した後も続く。だからこそ、夢のある未来を擬似体験させてあげて、そんなふうに頑張って生きていこうと思って入職するきっかけを作ってあげることこそ、本当に必要な教育と思うのである。そしてそういう人が少しでも増えれば、これからの日本の建築業界も少しは豊かな作り手が持続すると思うのである。